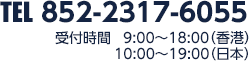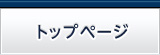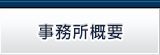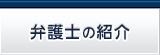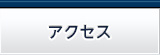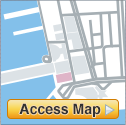香港にある資産の相続手続き(Probate プロベイト)③
- 2025年05月12日
- カテゴリ:コラム
③ 遺産管理(遺言管理)
①・②のコンビネーション つまり、遺言があったものの、
- 遺言の中に誰が執行人(Executor)であるのかの記載がない
- 或いは、遺言で指定された執行人が管理する権利を放棄した
- 或いは、該当執行人が遺言人より先に亡くなった
- 執行人が生きているものの健康精神的に執行人としての義務を果たすことが不可能な状態などの場合です。
C 死亡地
香港、日本或いは他の外国でお亡くなりになったのか。により必要な書類は異なります。 ドミサイルを日本とした場合には、日本の法律も絡みます。私が依頼を受けた場合は、香港の裁判所で求められる内容と細かな形式に基づいた日本法の意見書を作成し、日本法の弁護士に内容を確認してもらい公証してもらいます。香港のプロベイト裁判所は、かなり形式に細かく、担当者によって毎回異なる質問や補正が求められたりします。香港にとって外国人である日本人の相続手続きに慣れていない弁護士だと度々やり直しさせられその度に公証費用が発生してもおかしくありません。 日本人で死亡地が日本や香港以外の場合は、全ての地域が異なるために更に相続手続きが難しくなります。
D 相続税
2006年2月11日以降の死亡であれば香港の相続税は必要ありません。もちろん日本居住者や日本の財産(*詳細は表を参照)は、日本で相続税が発生します 。 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告納税が義務付けられており、遅れると延滞税や加算税まで上乗せして支払う必要があります。全世界に資産がある資産家の方は、相続税の計算のためにも各国の資産を確認する必要があります。 銀行や証券会社は、守秘義務のために、名義人以外の例え相続人からの問い合わせであってもなかなか答えてくれません。その場合は、香港の代理弁護士として香港の相続資産の調査や手続きに関してはお任せください。相続税に関しては、日本の税理士の中でも、海外相続の経験がある税理士に確認された方が良く、必要があればご紹介致します。
(国税庁HPにより抜粋)
上記の表中、居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者の区分に該当する相続人が相続または遺贈により取得した財産については、国内財産および国外財産にかかわらず、すべて課税対象になります(ただし、上記の表の※1の区分に該当する相続人が、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に非居住外国人(注5)から相続または遺贈により財産を取得した場合には、国内財産のみが課税対象となります。)。
居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者の区分以外に該当する相続人が相続または遺贈により取得した財産については、国内財産のみが課税対象となります。
E 相続財産内容
故人が香港で所有していた預金、法人株式、証券、不動産など一切の資産は、死亡時点で何れも凍結され、香港裁判所でのプロベイト手続き完了後、遺産管理状命令書(Letter of administration)もしくは遺言の検認(Grant of probate) がなければ動かせません。こうした日本との違いを知らない日本人の相続人が、日本と同様に考えられ、遺産分割協議書を携えられて香港の銀行まで向かわれるケースがあるようです。しかしながら例え遺産分割協議書や戸籍謄本を翻訳していたとしてもこれらは認められず『香港法の弁護士を探して下さい。』と言われてしまうのが現状です。香港では、日本人に限らず必ずプロベイトの手続きを経たのちしか資産は動かせません。尚、亡くなられた後、法的な手続きを取らずに勝手に資産を移すと、罰金及び禁固刑もありえますのでご注意下さい。
こうして 相続人から当事務所にご依頼を頂きますと、香港にある資産と負債をまずは確定させます。事前に故人からどこに資産や負債があるか聞いていないと、そもそもどの金融機関にいくらあるのかがはっきりしないというケースも少なくありません。最近は、エコのために郵送が少なくなっていると尚更気が付かないケースもありそうです。相続人からの『○○にあるかも。』という不確かな情報を頼りに、1件1件確認していく必要があり、金融機関によっても必要な書類が異なるため手間と時間がかかります。
忘れがちですが、香港で働かれていた方の場合は、MPFや翌年分の予想税金分にも資産が貯まっています。もし銀行の金庫も保有されている場合は、弁護士立会の元、金庫を開きますので更に手間暇がかかります。この手間は、金庫 の安全性と引き換えですので仕方がないですね。
F 相続手続きにかかる時間
相続手続きは、相続争いがなく順調な場合でも、1年から1年半はかかってしまうことも珍しくありません。裁判所からの質問段階をクリアし、遺産管理状のドラフト命令が出て、ドラフトを提出してから命令書が発行されるまでに3ヶ月もかかることもままあるからです。ただし相続管理人が高齢の場合には、裁判所も考慮し特別に通常より早く処理してくれます。
G 香港に資産のある日本在住者の相続
今まで当事務所で請け負った案件で圧倒的に多いパターンは、日本人で日本在住者が遺言書なしで争いなくお亡くなりになるパターンです。日本人が中国やシンガポールでお亡くなりになった、或いは、被相続人が香港人で相続人が日本人などのケースも様々手がけた経験がありますので、まずはご相談下さい。 お亡くなりになった方が香港の〇〇銀行に資産があることは薄々分かるが、いくらの資産があるか分からず、弁護士費用をかけてまでプロベイトの手続きをするべきかお困りの方もいらっしゃいますが、香港の銀行へ資産の問い合わせを代行することは比較的費用をかけずにできます。まずは資産を確定させてからプロベイト手続きを行うかを決めてもよいでしょう。
遺産管理人が申し立てをする場合は、相続裁判所から、遺産管理人以外に香港にいる保証人を求められます。しかもその保証人は、各々香港に被相続人の財産以上の資産を有している必要があり、万が一遺産管理人が裁判所の規定する義務に違反する場合は、他の相続人が被る損害を賠償することを保証する必要があります。香港の弁護士に委任することで、この保証人や保険料(もちろん条件あり)が免除されます。
香港の相続手続き自体は、我々のような香港弁護士に依頼される場合は、香港にお越しにならずとも手続きを全て完了することが可能です。その後の各金融期間からの資産の移転や香港法人の株式譲渡などの手続きに関しても通常は、香港にお越しになることなく対応することができます。
なお、争いのない相続認証規則(香港法律第10A章の第3条および4)により、有料無料を問わず、相続人、あるいは、香港法の弁護士以外の者が、香港の相続業務を代行・サポートすることは禁じられておりますので依頼をする場合は、資格者(香港において登録更新している香港法弁護士)かどうかにお気をつけ下さい。
タグ:HSBC, プロベイト, 会社, 国際相続, 手続き, 日本人, 相続, 相続税, 解約, 遺言, 銀行, 香港, 香港預金